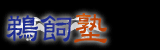
| トップページ / 道具 |
 |
篝(かがり) 鉄製の篝火に使う道具です。 この中に松割木(篝火用の松の割木)を 入れて篝火を燃やします。 金属のため熱が加わると、変形することも あるそうです。 |
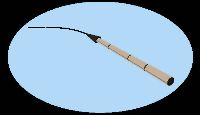 |
篝棒(かがりぼう) 篝をぶら下げるために使う道具です。 |
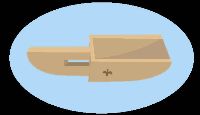 |
アカカイ 鵜飼をしているときに 鵜舟の中の水を外に掻き出す道具です。 |
 |
松敷(まつしき) 篝火に使う松割木を置くために 使う道具です。 大、小、二つの種類があります。 |
 |
櫂(かい) 鵜飼をする際に鵜飼舟で進む時に 使う道具です。水を掻いて進みます。 とも乗りが使う道具で ときどき、魚が居ることを知らせる 合図を出したりすることにも使われます。 |
 |
風折烏帽子(かざおりえぼし) 鵜飼をするときに鵜匠が頭に被る道具です。頭や眉毛を篝火から守るために被ります。 頭に巻き付けた時の形がちょうど風に 吹かれて折れているかのように見えることからこの名が付いたと言われています。 |
 |
諸(もろ)ぶた 鵜飼で捕れた魚を入れるために 使われる道具です。 鵜飼で捕れた魚は一度「吐け籠」に入れられ、その後、諸ぶたに魚をただしくきちんと 整えて並べます。 |
 |
足半(あしなか) 鵜匠が鵜飼を行うときに履く道具です。 草履とは違い、かかとの部分が無い 短い草履のことです。 鵜飼に使われるだけでなく、農作業などの野良作業や水場で使われたりします。 |
 |
風折烏帽子(かざおりえぼし) 鵜飼をするときに鵜匠が頭に被る道具です。頭や眉毛を篝火から守るために被ります。 頭に巻き付けた時の形がちょうど風に 吹かれて折れているかのように見えることからこの名が付いたと言われています。 |
 |
鵜籠(うかご) 鵜を運ぶための道具として使われます。 割竹(竹を縦に半分に切ったもの)を使って、編みつくります。 鵜飼を行う時には、もう一つの小さい鵜籠と一緒に持っていきます。 |
Copyright (C) 2009. GifuSogoGakuen. All Rights Reserved.